
右の写真を見るとよく管理された放牧方式で植物の生育が良いのが分かる。
|
千葉県有機農業推進連絡会 有機ネットちば |
||||||||
| ホーム | 空散 | 入会 | 遺伝子組み換え | 論点 | 食べ物と 健康 |
イベント | 遺伝子組み換え | リンク |
環境には、人体を基準に内部環境と外部環境がある。 内部環境は体内の環境で食べ物、水、年齢、体調などによって変わるが、それを養う外部環境と切っても切れない関係にある。 内部環境を外部環境から供給される食品、水、空気、人間関係等によって支えられるため、それらの健全さが直接身体の健全さに繋がっている。
外部環境には、一般的環境と農業環境の問題がある。 一般的環境は、産業や工業によるものや個人の家庭から出るものの汚染。 農業によって発生する、農薬・化学肥料、薬剤等化学物質によるもの、畜産廃棄物、耕作地の造成などによる環境破壊や単一作物の大規模栽培などによるものなどがある。
近代畜産では、大量の畜糞が小さな土地にあるため資源としての活用されるよりも「廃棄物処理問題」を起こしていて、臭気、地下水汚染、地表流出を無くすために大金を使っている。 それと対照的に放牧している場合は、糞尿は広い牧場に散らばって栄養分が直ぐ使われる。

右の写真を見るとよく管理された放牧方式で植物の生育が良いのが分かる。
航空写真は、T.O. 畜産(アメリカ、写真をクリックすると拡大)の牧場のものだが、これは放牧を始めて一年経っていない時のもので、大きな三角地帯が写真中央の下の部分に見えるが、ここが放牧されたところ。周辺の薄い緑の部分は肥沃度が低く休ませているか放牧期間が短い部分。
巨大な養鶏場では、鶏の食欲を刺激し飼料効率を高めるために砒素を与えている。 デルマーバ半島(デラウェア、メリーランド、バージニア)の6億羽の鶏は15億キロの生糞を毎年排泄するが、これは20-50トンの砒素を排出することになる。
放牧養鶏では砒素やその他の成長促進剤は与えない。
工場畜産の牛やバイソンの飼料の大部分はGM穀物になっている。ニューヨークタイムスの8月22日の記事では、GMコーンが益虫に害がある新たな証拠があると報じている。 研究者が、GMコーンを大カバマダラの幼虫にGMコーンを与えたところ、GM花粉のついた葉を食べた幼虫の20%が死に、正常なコーンの花粉がついた葉を食べた幼虫は一匹も死ななかったのだ。
穀物で育てるよりも牧草で育てることの根拠がここでも証明されている。
乳価が低いため酪農家の存続が困難になっており、利益を増やすために家畜を増やすのが一般的になっている。 しかし、頭羽数を増やすことはそれだけ畜糞による過剰窒素やリンを排出することになる。 ペンシルバニアのUS地域牧場調査グループが環境に優しい頭羽数の増やし方を調べたところ、しっかり管理された放牧をすることが「農家にとって利益があり、かつ窒素が地下水に流亡するのを最小限に食い止めることが出切る。 この調査結果では、酪農家は放牧場を拡張したり収穫を計画する場合にローテーションすることを考慮に入れるべきことを示している。」と結論した。ウィスコンシンの酪農拡張の際の作物選択例.
オレゴン州立大学の研究によると、肥料の流出レベルの亜硝酸塩が含まれる水槽でお玉じゃくしと蛙になったばかりのものを飼った所、食欲が無く、奇形、麻痺が発生し仕舞いには全て死んでしまうことがわかった。 普通の水の入った水槽の対象群は一匹も死ななかった。 「非常に低いレベルの亜硝酸塩量だったので影響があるとは思わなかった。」と動物学教授のアンドリュー・ブロースタインはいう。 EPAは研究結果を見るまではコメントできないという。1999年12月号環境毒物化学誌に発表
適切に管理された牧場の地下水からは、亜硝酸などの汚染物質が全く無く近くの山林からの水と変わらないことが分かっている。
二酸化炭素ガスなどの温室効果ガスが大気中に増えて世界的気候変動を起こしている。 牧場の牧草やマメ科植物は空気中から二酸化炭素を取り除き「炭素捕捉」現象によって炭素を土中に蓄える効果が高いことが分かった。 大平原の牧場地には炭素が40トンあるのに対し、耕起栽培地では26トンしかない。 近年政府の保全地域計画によって、作物栽培された土地を牧草地に戻すようになっている。牧草地に戻すことによって最初の5年間に年平均エーカー当り500kgの炭素が増える。 この保全地域計画で3,600万エーカーが牧草地に変えられたので1,800トンの炭素が空気中から除去されたことになる。
地球温暖化の議論が活発化するにつれて、反芻動物が出す温室効果ガスに注目が集まってきている。 ルーメン消化の副産j物であるメタンガスが、二酸化炭素よりも温室効果が高いことによる。 しかし、メタンガスも多様なガスの一部であってそれがどれほどの影響があるのか放牧と飼料飼育での違いあるのか等分かっていなかった。
環境教育研究所が行った調査によると、畜舎飼育のものが放牧した場合よりもメタンガスの発生量が少ない(表中ではenteric)ことが分かったが、牧草が「炭素捕捉」効果があるため右端の棒グラフで示される合計では温室効果ガスを吸収していることになる。 逆に、畜舎飼育の場合は温室効果ガスの発生に重大な影響のあることが分かる。
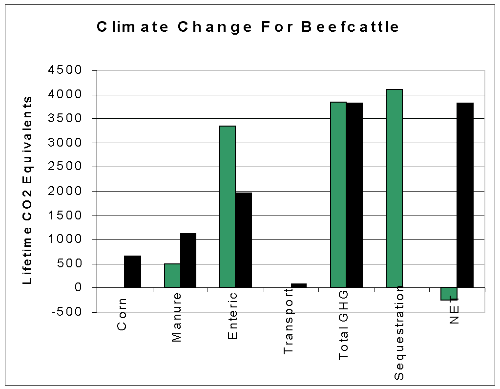 棒グラフ 緑=牧草飼育、黒=畜舎飼育
棒グラフ 緑=牧草飼育、黒=畜舎飼育