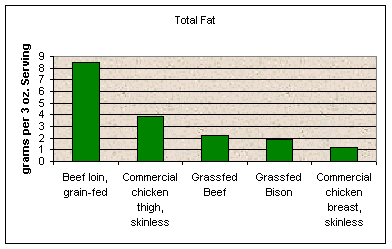 図1
図1|
千葉県有機農業推進連絡会 有機ネットちば
|
||||||||||||||||
畜産
| 畜産物の質 | 近代飼育法の弊害 | 自然の恵みを再認識する | 自然養鶏 | 牧草飼育とは |
自然に根ざした畜産とは、まず家畜が最も自然に近い状態で生きられることが大前提です。 人間が自然の恩恵を家畜を通して得る事は二の次。 というのは、それが人間にとって最も畜産の恩恵をもたらしてくれるからです。 動物には単に流通目的のために有機と定義されている飼料ではなく、自然な本来の食べ物が必要です。
野生の動物は、例外なく自然の中を走り回り、草を食み虫を動物をその糧として生き本能的に子孫を守っています。 つまり、牛、羊、鶏、豚など家畜化された動物は皆放牧地で栄養を得て来ていました。 そうすることで遺伝的特徴を培い現在にいたっているのです。 いかに品種改良しようとも屋内で運動せず濃厚飼料に抗生物質、合成ホルモン剤、治療薬をサプリメントとして生きれる様にはなっていないのです。 ところが、そのように品種改良しているから大丈夫と農学者、畜産業者、医動物薬会社は動物虐待を正当化するが、動物福祉に反しそれを食べる人間の健康をも害するものでしかありません。
畜産物の質
畜産物の質は、その放牧地の質で決まります。 質とは、いかに生命力が豊かで健康に生きていた動物の肉、乳、乳製品であるかということです。 当然、抗生物質、ワクチン、ホルモン、その他の医薬品などの使用は論外である。 牧草や放牧地の質は何で決まるかというと土の質であり、土の質はその腐植と土壌の組成できまる。 結果として、そのように飼われた家畜の畜産物を戴く人間が健康に医者要らず、病気知らずで暮らせることは世界のあちこちで証明済みです(プライス・ポッテンジャー栄養基金参照)。
しかし、穀物、それも疲弊した土壌で生産され、かつ遺伝子組み換えされたものが飼料の主体となり、牛やヤギ・羊など反芻動物の繊維質を何度も噛み直して分解吸収する内臓をボロボロにしてしまっているのです。 従って、当然の事ながら抗生物質や医薬品なしでは飼育が出来なくなっています。 放牧飼育の家畜はその生産量は、工場畜産とは比べ物にならない。 しかし、その健康への貢献度や環境との調和を経済指標に取り入れるならば、月とすっぽんほどの違いで、自然放牧畜産が優れていることは言うまでもない。 そして、そのような飼育のみを行った時に生産できる量を人間が戴くということにしなければ自然生態系を守ることも農業環境もそして健康も守ることは出来ないのです。
畜産物を考える場合、その質を第一とし、また土壌の最適な生産力を考え合わせ耕種農業との兼ね合いを図りながら適切に組み合わせることで健康な人口を養うことを最終目的とすべきでしょう。
近代飼育法の弊害
反芻動物には、澱粉質を分解する酵素がないため穀物食に慣れず、慣れても様々な障害が残ります。 鼓張、アシドーシス、蹄葉炎、、肝膿瘍、毛細血管拡張症、突然死症候群などの発生を抑えることが出来ないため抗生物質、動物医薬の使用を避けられないのです。 抗生物質多用による耐性菌の蔓延も重大な問題です。 抗生物質に耐性のあるサルモネラ菌もたくさん増えてきています。 アメリカのファーストフードチエーン店でこれによる中毒で多数の人が死亡したことはまだ記憶に新しい。 この耐性菌に効く薬を開発することで動物医薬業界は潤っており、逆に人間は抗生物質耐性菌のためにある病気に罹ったら病院から抜け出られないという状態になってしまうのです。
合成ホルモン使用も問題で、成長ホルモンを使うとインシュリン様増殖因子;IGF-1の量が牛乳に多くなり、これが殺菌乳では更に増えて、乳癌や消化器癌との関係が疑われる状態になっています(1)。 飼料用トウモロコシや大豆の栽培には、農薬が大量に使われており、これが畜産物に残留しています。 狂牛病なども畜産廃棄物を蛋白質には変わりないということで草食の反芻動物に与えるというとんでもない誤解釈で起きたといわれているが、これも地力のない所で大きさだけを満たした栄養の偏った飼料を与えた結果と考えて間違いではないだろう。 このようなことを許した農学、畜産学、栄養学にも常識が通らない浅薄な科学の限界が見えてくる。
アメリカでは野生の鹿にも慢性消耗病や脳の萎縮やスポンジ化を示す狂牛病ならぬ狂鹿病が出ているが、これもアメリカの自然全体がいかに野生の動物をも養えなくなっているかの証拠だと思う。 つまり、農薬や化学肥料を使った狩猟動物(ゲーム)なのだ。 もちろん、意図して撒いていないだろうが、大規模農場の空中散布したものが、山岳部に気流で流れ着きそこを住処にしている動物たちの棲息地一帯を質の悪い牧草にしているためだと思われる。 人間もこのような疲弊した土壌の生産物だけを食べているとアルツハイマーにもCJDにもパーキンソン病その他の神経精神病にも当然なってくる。 脳神経系に必要な栄養がないからだ。 それは食べるものに欠落しているのが原因だ。
本来病気は、細菌や病原菌が居るからなるのではなく、細菌を撃退するための免疫力や体力が人間や動物にないためで、それは食べるものにそれらの力をもたらす栄養がないからだ。
病気は栄養失調、栄養不足を示す目印のようなものだ。 従って細菌を退治しようとするのは、対症療法であって原因治療ではない。 その対症療法が大手を振ってあたかも原因療法であるかのごとくに誤解されたために、異常に殺菌剤や農薬、ワクチンなど不要な物が増え、肝心のいかに栄養豊かな健康な植物、それを培う土壌を豊かにすることが蔑ろにされてきた。 これが医学が発達し,医療という本来補助的であるべきものが幅を利かし中心に座る結果になっている。 これ全て農業がその本筋を見失い、利益のために形ばかりのものを作るようになったためである。
というか、本来の農業、自然のもたらす偉大な恵みを充分に認識しなかったか伝えてこなかったためである事が大きいかもしれない。 かくして私たち現代人は、この自然の偉大な恵み、母なる大地の示すところを再確認することとそれを後代へ伝える事業を始めなければならない。
自然の恵みを再認識する
自然な肥沃な土壌で育まれた牧草を食べた牛の肉は脂肪が少なく、また脂肪もオメガー3脂肪酸が豊富である。 オメガ3脂肪酸にはアルファリノレイン酸、魚の脂肪分であるDHA、EPAがあり、これはガンの予防、循環器障害の改善、肥満防止、糖尿病予防、免疫不全の減少などの効果が最近分かってきている。 逆に穀物主体の牛ではオメガー6脂肪酸(リノレイン酸もこの内)が多く出来、これがその牛の肉や乳に出てきて結果的に今、一般的に医療関係者が口を揃えて忠告する動物性食品の害が出てくる。 つまり、心臓循環器障害、高脂血症、糖尿病、癌が多くなり、精神神経への影響では、欝、攻撃性、多動症、分裂病等に影響を与える。
オメガー3脂肪酸は食物の緑色部で生成され、オメガー6は種子に多く生成される。
1940年代には一頭の牝牛は一産するたびに量の多いので約2,000Lだったのが現在では約7,700Lと約4倍近くなっている。 これは成長ホルモンと、抗生物質の多用による結果で、この量は一頭の子牛に必要な量の20倍もの量に当る。 しかしこのように害の多い脂肪酸を多く含む牛乳では、その子牛に退化病が発生するのは必須で、代を重ねる毎に虚弱化し、いづれは全く子孫が生まれなくなるか、生まれても育たなくなり死に絶えることになることが懸念される。
牛の生産する乳は、6月の新芽の頃のものが最も栄養価が高いとされている。 この頃の乳には、特別の成長因子があり、バターやチーズは色が濃いオレンジ色になる。
| オメガー3脂肪酸 ・オメガ3脂肪酸は、植物の緑の部分で生成される。 ・穀物食の牛よりも2-6倍牧草食の牛のほうが多い。 ・オメガー3脂肪酸には、DHA,EHA,アルファ・リノレン酸等がある。 ・アルファ・リノレン酸は共役リノレン酸LNAと呼ばれ、 植物体にある油の60%がこれ。 ・CLAは、オメガー6脂肪酸であるリノレン酸(LA)とよく似ており、 CLAでは18ある炭素の二重結合部が9と11の間にあり、 一方のリノレン酸は、9と12の間でこの僅かな違いが大きく 生体内での働きの差になっている。 ・最近はサプリメントで合成CLAが出ているが、これは有害である。 ・脂肪を燃やして利用する |
オメガー6脂肪酸 ・オメガー6脂肪酸(リノレン酸もこの仲間)は、植物の子実部に 生成される。 ・生体内ではオメー3とオメガー6が等量くらいが丁度良いとされ ている。しかし、現在の食事には、植物油が異常に多く、 オメガー6脂肪酸のほうがオメガー3よりも圧倒的に多い人が大部分。 ・生体内では、高脂血症、心臓循環器障害、神経精神障害、癌、 肥満などが増える。 脂肪酸は、生体に欠かせないもので、体内の ほとんどの細胞で必要とされている。 ・脂肪が利用しにくい。 |
|
この他に、放牧牛の栄養的恩恵には:
・脂肪が少ない、
・カロリーが低い、
・オメガー3脂肪酸が多い、
・アルファ・リノレン酸が多い、
・ベータカロチンが多い、
・大腸菌の汚染が低い、
・ビタミンやミネラルが豊富、
・抗生物質、合成ホルモン、残留農薬がない などの特徴がある。
これらは単に科学的に調べられる範囲のことで、実際の健康を全体的に測る物指しはない。
科学的に証明できることを唯一の現実かのように考えている人が多いが、自然の感性を失った我々現代人は、身体で感じる健康や環境の変化を知る能力を再構築しなければならないのではないか。
自然養鶏
鶏も放牧することによる健康への貢献は、科学的な証明がなくともその姿を見れば分かる。 あらゆる食べ物がそうである様に単なる詰め物ではなく、命を育むものであるから、その生命力は重大な要素である。 毛艶、孵化率、肉だれ、鶏冠の血色、勢い、動き、性格など判断材料は色々あるが全て良識的なことで、科学的に数値で表さなくともその健康度は見て分かるものだ。
鶏の場合は、反芻胃がないので植物だけでは栄養が足りないため、土を掘り返して微生物や昆虫、地虫の類いを摂取しなければならない。
自然に飼われた鶏の脂肪はやはり、オメガー3とオメガー6が理想的な1対1の割合である。 穀物で育つとこれが1:20と極端にオメガー6が多くなる。 基本的に動物は食べ物を調理しないので生のものにあるビタミン、蛋白質、酵素、核酸、有機酸などありとあらゆる栄養素とミネラルをそのまま利用できるようになっている。 植物にはまた、ベータカロチンの多いものが多く、必然的に卵の黄身は黄色が濃くなりオレンジがかってくる物もある。 冬場には青草が減る地方では、色が褪せてきてしまう。 しかし最近ではケージ飼いの鶏でも色が出るような成分(パプリカ、色素等)を餌に混ぜているため自然のものとは見分けがつきにくくなっている。かえって最近では、ケージ飼いや大規模養鶏の方が均一に濃い色が着き、自然養鶏のものは、青草の量や季節によってばらつきがあり、一般市販のものよりも色の薄いものが多い。
自然に飼う鶏の場合、ワクチン、抗生物質、ホルモンなどはもちろん必要ない。 草を食べて育つ鶏の卵にはケージ飼いの鶏のものに比べて脂肪が10%少なく、ビタミンAが40%多い、オメガー3脂肪酸が400%多い、コレステロールが34%低い等の特徴がある。
畜産の今後
我々に課された課題は、自然で肥沃な土壌に育つ植物を食べる動物の生産物による健康を証明することと、その経済性を医療費、環境復旧費などを考慮した生産費によって優位性を証明することだろう。
今の多くの有機農家がそうであるように、自作の素晴らしい農産物の価値を、市販品を食べる習慣や自家産品も不適切な加工、調理によって台無しにしてしまい、一般の人と同じに病気になり寿命もさして変わらず、死ぬ時も寿命ではなく、病気で死ぬという状態では、何の証明にもならないし有機農産物を奨めるにも説得力がない。 有機農業を信じ奨めるのであれば身を持ってその優位性を証明しなければならない。
一般的に家畜は、誕生後数ヶ月を牧場で過した後、飼育農家に運ばれて穀物主体の畜舎飼育となる。 そこでは、ホルモン剤、飼料添加物、成長促進と蜜飼いや不自然な飼料によるストレスの害を少なくするために抗生物質が投与される。 乳生産量を増やすために合成ホルモン注射もされる。
ここでいう牧草による飼育法は全く違う。 まず家畜は誕生から出荷まで同じ牧場で暮らす。 反芻動物(牛、羊、やぎなど)は、質の高い牧草地で青草を食み、冬期や旱魃の時には干草やサイレージを食べる。 ほとんどストレスがないので人工医薬を使う必要がない。 成長は、ホルモンや成長促進添加剤の量ではなく、牧草の質や量による自然に任される。
放牧飼育は、畜舎飼育よりも技術や知識が必要。例えば、肉質が柔らかく多汁にするには、特に出荷数ヶ月前の牧草の質が高くなければならない。このためには土が肥沃で有機質が多くなければならない。 牧草の質と量を維持するために食べ方に気をつけて特定の場所が食べられすぎたり、食べられなかったりしないようにする必要もある。
一般の鶏や豚は一生畜舎内で過ごし、檻に詰め込まれたり、畜舎内にギュウギュウ詰にされたりしている。 最短で経費が最少で市場に出せる大きさになるように餌や環境を管理する。 密飼いで急速に広まる病気や成長を促すために抗生物質や成長促進剤が使われる。
放牧豚や鶏は、屋外の牧草地で飼われる。 鶏は30%近くの栄養を草で摂り、豚もよく草を食べる。 こういう飼い方の肉や卵では、ビタミンE、ベータカロチン、オメガー3脂肪酸が多くなリ、脂肪が少なくなる。
認証有機畜産では、飼い方よりもホルモン剤、抗生物質、農薬の使用しないものに焦点があって、本来の牧草ではなく穀物を与えている場合が多い。 反芻動物に穀物を与えると健康を害し、肉質も落ち栄養価が下がるばかりでなく環境にも害がある。 これは、穀物の栽培法が有機であろうと科学農法だろうと変わりがない。 最も健全な畜産物は、動物が本来の生き方や食べ方をしたものからしか得られない。
オメガー3脂肪酸と共役リノール酸(CLA)を左右するもの
牛乳中の有益なCLAやオメガー3脂肪酸の量は、品種、個性、年齢、季節などに影響される。 また、飼育する地域の気候にも影響される。寒い地域の牛乳やチーズにはオメガー3やCLAが多い。 これは植物にある耐冷力(=寒冷状態でも凍らない)を形成するオメガー3脂肪酸が多いためでこれが体内でCLAに変換される。 最近の研究では山岳部のものが平地部の牛乳よりも約2倍多いという報告がある。
牧草飼育の牛は穀物飼育の牛に比べて総脂肪量が少ないが、オメガー3脂肪酸は2-6倍多い。 オメガー3脂肪酸は、心臓と相性がよく血中にオメガー3の多い人は高血圧や心臓病になりにくい。 脳神経にも良い働きがあり、欝や分裂病、多動症、アルツハイマーには掛かりにくい。動物実験ではがん抑制力も確認されている。 オメガー3脂肪酸は脂肪を燃やす働きがあり、脂肪による体重を減らすことが出来る。 海産物に多く魚油、それに亜麻仁油、胡桃等の種子やナッツそして牧草飼育の動物の脂肪にある。 理由は食物の葉緑体で作られるためで、植物体の脂肪酸中60%はオメガー3である。
注1: 国際健康サービスジャーナル26(1):173-85、1996年エプスタイン・S・S『成長ホルモン投与牛の無表示乳:畜産の監督放棄』
牧草飼育の畜産物には、脂肪が少なく、ビタミンE,共役リノール酸(CLA)、オメガー3脂肪酸が多い。 以下に若干の比較を示す。
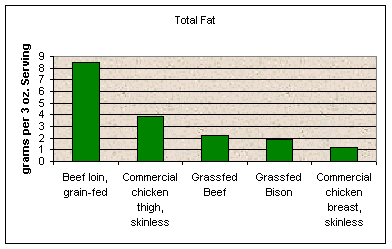 図1
図1
図1は、総脂肪量で左から穀物牛のロイン、市販の皮無し鶏腿、牧草牛、牧草バイソン、市販鶏の皮なし胸肉の100gあたりのもの、縦軸は約90gあたりの脂肪量(g)。
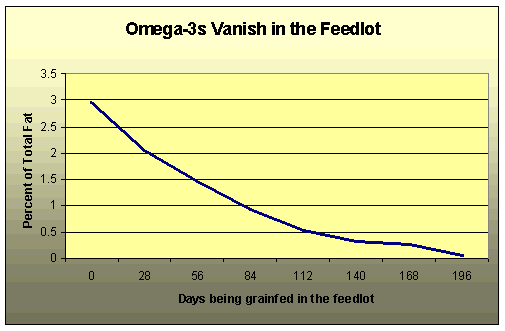 図2
図2
図2は、オメガー3脂肪酸(縦軸%)と穀物給与日数(横軸): 総脂肪に占める有益なオメガー3脂肪酸の量が穀物飼育日数の増加と供にどんどん少なくなってくる。
(出展: Duckett, S. K., D. G. Wagner, L. D. Yates, H. G. Dolezal, and S. G. May. "Effects of Time on Feed on Beef Nutrient Composition." J Anim Sci 71, no. 8 (1993): 2079-88.)
鶏も鶏舎内で飼い緑餌が無くなるとオメガー3脂肪酸が減る。 牧草飼育の卵では工業養鶏のものに比べオメガー3脂肪酸が約20倍にもなる。 近代食に有益な必須脂肪酸が少ないのは緑餌から穀物に代えた事が原因である。
共役リノール酸(CLA)は、ガン抑制力が強い事が分かってきている。
ビタミンEは以下の図で示すように穀物餌の肉よりも4倍多い。
図3は左から穀物で畜舎飼育、穀物で合成ビタミンEを高用量で添加(1,000IU/日)、牧草飼育の順。ビタミンEは、抗酸化力が強く心臓病やガンや老化の予防になると言われている。
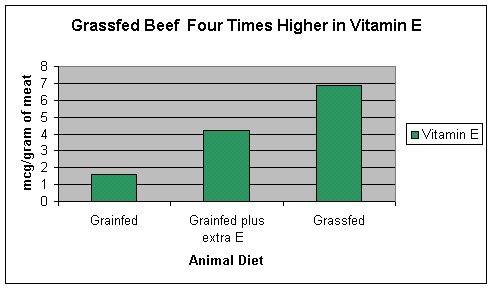 図3
図3